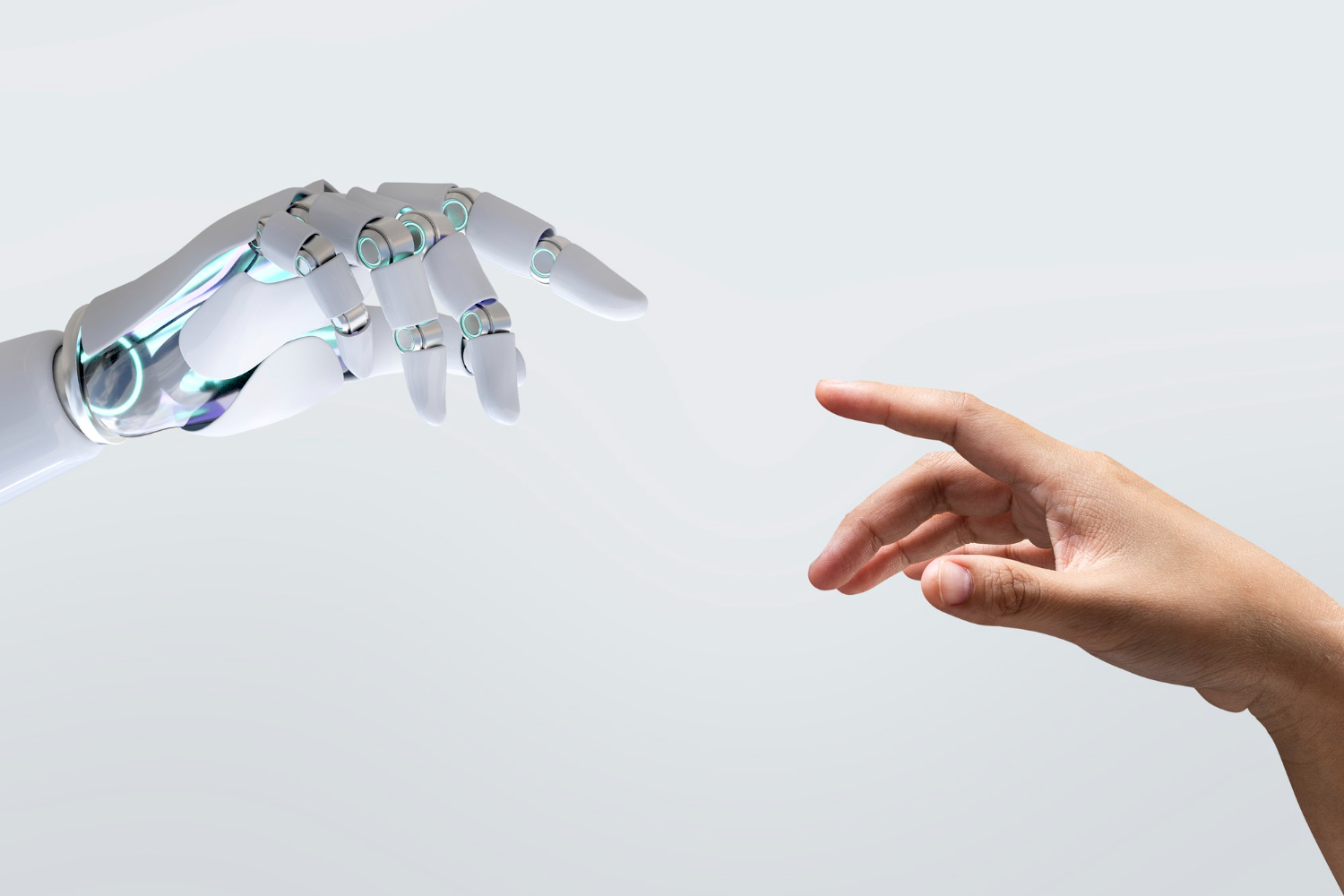映像表現の「共創」と「本質」ってなんだろう。
映像制作の現場は、今、かつてない大変革期を迎えています。テキストから映像を生成するAI、自動編集、リアルタイムのカラーグレーディング、シナリオ提案、機械音声によるナレーションなど、AIテクノロジーの進化は、クリエイターの役割と仕事の進め方を根底から変えつつあります。
このAI時代において、映像クリエイターは「AIに仕事を奪われる」のではなく、「AIを使いこなし、人間の創造性を極める」新しいステージに進んでいます。
という上記の文章も実はGEMINIに書いてもらっています。AIは昨今私含めてクリエイター職の人でも使っている人が回りにもかなり多いのですが、その使い方にうーんと思う部分もありながらも確かにそうだなと思わされるところも多々あります。そのあたりのモヤモヤを本記事で紐解いてみようと思いました!
映像編集において私が重宝している部分でいうとグラフィックデザインを動かす(自分でも出来るがめんどくさいことをやってもらう)、ナレーションを収録して貰う前に映像の尺を合わせたいので機械音声で仮ナレーションを収録する(後で尺調整発生したらめんどくさいので)、3DCGを起こしてもらう(3Dを作る技術がないのと発注すると高くなってしまう、頻度が少ないのでリソースを探すのにコストをかけたくない)などは凄く助かっています。
映像のお仕事以外だと、マーケティングで分析を行う時に平準的な感情のない調査を行いたい時や、画像の幅が足りないので伸ばしたいとか、ちょっとしたコーディングの記述など自分がやる必要がないものや、自分より早く出来るものをAIにはお願いするようにしています。
逆に絶対に任せられない部分でいうと、方向性を決める・ビジュアルの品質を管理するなど判断を軸にしなければいけない分野については、今のところは人間じゃないと出来ないと思っています。というより、それがクリエイティブで人間的な仕事の営みと考えると同時に、「AIに任せたくないといういらぬプライド」というのも正直あるのかなと思っています。
それではAIに書いてもらった文章を再度見てみましょう。

AIが映像制作にもたらす「革命」
AIは、映像制作における時間とコストの制約を劇的に取り払っています。
| 制作工程 | AIの具体的な役割 | クリエイターへの恩恵 |
|---|---|---|
| アイデア/企画 | 膨大なデータからトレンドや視聴者の好みを分析し、最適なコンセプトやシーン構成を提案。 | 企画の質と速度が向上し、クリエイターはアイデアの「意味づけ」に集中できる。 |
| 素材生成 | テキストプロンプトからハイクオリティな背景、エフェクト、あるいは動画シーンそのものを生成。 | ビジュアルコンセプトの具現化が迅速化し、低予算・個人でも大規模な表現が可能に。 |
| 編集/ポスプロ | 自動カット割り、被写体抽出(ロトスコープ)、カラー補正、ナレーション(音声合成)。 | 反復的で技術的な作業から解放され、クリエイティブな「最終調整」に注力できる。 |
AIは、これまで「職人技」とされてきた多くの技術的な障壁を下げ、表現の民主化を進めています。
ということなんですがどう思いますか?
私は概ね理解はできますが、アイデア/企画と編集/ポスプロに関してはまだあまり信用していません。というのも、ある企画で芸人さんを使う企画があって、自分でもシナリオは作ったんですが案としてもう少し提案できればと思い、AIにシナリオを書かせて見たのですが全然その芸人さんらしさが出てなかったんですよね。(少し前の話なので今は良くなっていますが)
文献が少なく学べていない分野に関しては苦手なのかな?というのと、間というか行間の言語化みたいなものが感覚的にできないのかな?と思っています。
あとはカット割りやシーンの生成に関してもどうしても背後の設定みたいなものが薄いので違和感を感じたりしています。それは目で見るものや耳で聞くナレーションも含めてです。なので、「あっ、これAIだな」みたいなものを感じたりしています。マニュアルや大まかにわかれば良い映像なら良いんですが、感情を揺さぶりたい映像になると「この違和感」が邪魔になってしまうのでAIにはもう一息がんばって進化してほしいところではあります。
とはいえ、自分がプロンプト書くのが下手なだけかもしれないので一概には言えませんが個人的に感じた部分になります。
再びAIに書いてもらった文章に戻ります。
クリエイターの役割は「共創者」と「ディレクター」へ
AIが作業の多くを代替する時代、クリエイターの価値はどこにあるのでしょうか。それは、AIを「道具」として最大限に活用する能力と、**人間ならではの「創造の意志」**です。
(1) AIを操る「プロンプトスキル」と「選別眼」
AIに適切な指示(プロンプト)を与え、意図した結果を引き出す能力は、新しい時代の基礎スキルです。また、AIが提案・生成した複数の素材の中から、作品の**コンセプトに最も合致するものを取捨選択し、編集する「選別眼」**こそが、最終的なクオリティを左右します。
(2) 人間ならではの「視点」と「物語性」
AIはデータに基づいて最適な答えを出せますが、人間の経験、感情、文化的背景に基づいた「なぜその映像を作るのか」「誰に何を伝えたいのか」という本質的な問いに答えることはできません。
- 共感と感情: 人間の繊細な感情の機微を表現し、視聴者の共感を呼ぶ独自のストーリーテリングは、人間のクリエイターにしか創造できません。
- 倫理観と責任: 生成AIがもたらす著作権や倫理的なグレーゾーンに対し、クリエイターは社会的責任とディレクションの判断を下す役割を担います。
これに関しては完全に同意です。
先に書いた通りですが人間のクリエイティブが活きるのは、困っている人の声を聞いて、それがどのように社会や地域の役に立つのかを考え、よりよい伝え方を考え、表現手法に落とし込む部分だと考えています。
この時にAIで市場調査や情報収集を行い、判断材料として活用するというのが効率的な使い方だと思います。信頼性が高い部分とそうでない部分を人間とAIが補強しあい、良い提案をして色々な分野に役立てるというのが本来的な使い方なんではないかなと。
再びAIの文章に戻ります。
AI時代に求められる新たなスキル
AIとの共存が当たり前になる今後、映像クリエイターには以下の能力が一層重要になります。
- AIリテラシー: 各種AIツールの特性を理解し、効率的なワークフローを設計する能力。
- 企画・コンセプト力: 技術的なスキルよりも、「何を表現したいか」という独自の視点やテーマを深く掘り下げる力。
- データ分析力: AIが提供する視聴者データやトレンド分析を読み解き、次の創作に活かすマーケティング視点。
AIは、クリエイターを退屈な反復作業から解放し、真に創造的な活動に集中できる環境を与えてくれました。
AI時代における映像クリエイターは、AIという強力な共創パートナーと共に、人間の情熱と洞察に満ちた、新しい映像表現の地平を切り拓いていく存在となるでしょう。
これも、そのとおりです。
AIが儲かるからとか流行っているからとすべてを鵜呑みにするのではなく、あくまでツールとして使い「すなわち、それは一体何なのか?」という自問自答で最終的にコンセプト作りやクリエイティブに活かせるようにできるよう、人類とAIが良いパートナーになれるといいなと考えています。
とりとめのない記事かつAIの便利な使い方のような記事におらず、完全にポエムになっています。暗いニュースが多い中、面白い世の中になるといいなと願っています。